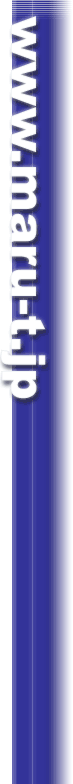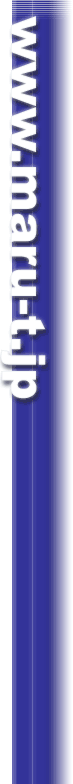 |
|
平成28年第4回定例会で、代表質問をしました |
 |
平成28年11月24日(木)、第4回定例本会議において、渋谷区議会自由民主党議員団を代表して、区政を取り巻く諸課題に対し、調査した結果を踏まえた提言も織り込みながら、
区長・教育長に大きく6点質問いたしました。ダイジェスト版の質問要旨と区長・教育長の答弁要旨を掲載します。
又別ウィンドウで質問の全文と録画した画像も併せて掲載いたしますので、ご覧いただければ幸いです。今後も区政発展のため、常に問題意識を持ち、真剣に取り組んで参ります。
平成28年度第4回定例会質問原稿
|
子育て・防災・地域コミュニティ等六点を問う |
 |
 子育てについて
子育てについて
問
二十八年の法改正により、児童相談所の設置に向けて準備に入るとのことだが、区長の考えと今後の対応を伺う。
区長
人材の確保等様々な課題があるが、虐待の緊急度に即した初動対応が迅速に行え、きめ細かいフォローが可能になる。今後は都と協議を行い、設置に向け準備を進める。
問
①子ども家庭支援センターと東京都の児童相談センターとの連携強化は。②警察等関係機関と有機的に機能することが不可欠と考えるが。
区長
①現在情報共有とともに個別事案の検討に参加するなど相互交流を図っている。②虐待対応時に関係機関に働きかけ、ケース会議を開催し、処遇方針の確認を行い、対応の漏れや認識の違いが生じることを防いでいる。
問
子ども家庭支援センター相談体制の充実や強化策は。区長 心理相談員活用のほか、社会福祉士など福祉全般に専門知識を持った職員を配置して体制強化とともに、東京都児童相談センターに職員を派遣して支援スキルの習得を図り、職員の育成強化に努める。
 防災について
防災について
問
熊本地震で得た教訓を反映し、現在策定中の受援計画の検討状況は。
区長
策定の基礎となる業務継続計画の策定に取り組んでいる。発災時に人員不足が生じる部署に応援職員を配置できるよう受援計画に反映させ、災害対策班の編成にも柔軟に対応できるよう検討する。支援物資集積場所を点検、運用方法を検討中。配送に関しても小回りのきく軽トラック所有の民間配送業者などと協定締結を進めていく。
問
車中泊の区民への検診体制等の対応を業務継続計画等に反映する考えはあるか。
区長
避難所の施設内への避難を基本としているため反映することを考えていないが、やむを得ず車中泊される方の実態を把握し、健康相談など対応の検討を図っていく。
問
平成三十年度に改定される地域防災計画は区民の理解があって機能する。区民周知に関する所見を伺う。
区長
マニュアルをまとめ、説明会の開催や区ホームページなどで丁寧な周知に努める。
問
少ない経費ですぐにでも実現可能な感震ブレーカーに対する助成を実施すべき。
区長
不燃化特区指定の本町二丁目から六丁目の木造住宅について、感震ブレーカー及びコンセントの助成をする。
問
木造住宅密集地の無電柱化整備を進める考えは。
区長
都の政策を踏まえ、引き続き国とも連携協議を進めていく。
 地域コミュニティについて
地域コミュニティについて
問
①町会・自治会を条例で基礎的団体と位置づけ、法的根拠のある団体として支援と強化を図るべき。②区が率先して無関心層への働きかけや若い世代への参加促進に関わることが必要では。③様々な支援策を今から拡充すべき。④町会・自治会の負担軽減のためミニマム化を図るべき。
区長
①町会の存在意義、町会活動への人的・物的支援、法人化への支援などを内容とする条例制定を実現したい。②地域SNS等を活用し、無関心層や若い世代に発信していきたい。③二十九年度予算にコミュニティ活動に対する支援を盛り込みたい。④地域活動が盛んなNPO法人等が町会や自治会の活動を支援できる取組をしていく。
 福祉について
福祉について
問
はあとぴあ原宿及び渋谷保育園に隣接する国有地を活用して、生活介護施設の新規設置と拠点施設の整備を。
区長
区内に不足しているリハビリ等の機能訓練施設を新設し、障害者福祉計画で位置づけている地域生活支援拠点を整備したい。はあとぴあ原宿の増設は施工上困難のため、渋谷保育園の建物と一体的に整備する。
 高齢者施策について
高齢者施策について
問
老朽化が進んでいる高齢者ケアセンターのあり方や整備について所見を伺う。
区長
建て替えて、特別養護老人ホームを含めた新たな福祉施設として整備する。
問
高齢者の運転免許証の自主返納を区が側面からサポートする観点から、ハチ公バスの回数券を配布するなどの施策を再度行う考えはないか。
区長
実効性のある施策を地元警察と協議し、検討する。
 教育について
教育について
問
代々木中学校が取り入れている発芽玄米給食を、生徒の問題行動に多少でも効果があるならば拡充に踏み切るべき。秋田県大館市との都市交流を踏まえ、区内業者育成の観点より渋谷区米穀商組合の協力を求めては。
区長
発芽玄米が白米に比べて高価であること、大館市との交流に基づき「あきたこまち」の供給を安価で安定的に受けていることもあり、教育委員会や学校と相談しつつ、まずは給食の特別メニューとして提供する機会をつくり、その成果をみて検討したい。
問
青少年海外派遣研修に参加した生徒が事前研修をして経験を踏まえた成果を自校に持ち帰り、在校生全体で共有することは大変重要である。各学校においてこうした成果をどのように生かしているのか。蓄積されたアーカイブ(*1)を編集して次世代を担う全区立中学生のために活用すべき。
教育長
各学校で行われている国際理解教育の際に、クラスメイトが体験した貴重な学びを教材として共有することで質の高い学びとなる。子どもたちの学びをまとめた報告書を各学校に配布してきたが、記録や映像をまとめて、過去の年度も含めて振り返ることは、子どもたちの異文化への理解を深める。所管の文化振興課が持つ映像記録を編集するなどして、次世代の在校生への国際理解教育に活用していく。
問
シリコンバレー青少年派遣研修は生徒が研修を終了した時点で新学期を迎え最上級生になる。いつの時点で在校生に還元する機会とするのか。
教育長
成果の発表の時期や方法については、子どもたちに過度の負担になることなく、より効果的なものになるよう文化振興課と検討している。
問
①オリンピック・パラリンピック教育についてどのような施策を展開するのか。②代々木山谷小学校の検証を受け、タブレット端末の今後の活用と中学校におけるプログラミング教育の位置づけは。③言語能力向上に向けた小学校での取組について伺う。
教育長
①特にパラリンピック教育を重視し、心のバリアフリーの浸透を図る。②単なるツールの一つでなく、協働学習の効果的な実施、知識の活用力と想像力を引き出す媒体として働くよう展開し、教育課程の中で明確に位置づけ計画的に進める。③ICT教育と国語・読書教育の相乗効果で言語能力の育成を図る。
用語解説 ※1 アーカイブ 将来に残すために保存された記録物や文書類


もどる
 © Takashi Maruyama
© Takashi Maruyama
|
|